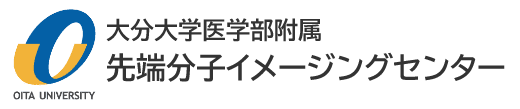臨床研究について
PETを用いた臨床研究について
PET検査は、体内での代謝や特定の分子の分布を画像化できる技術であり、病気の早期発見や病態の理解、治療法の開発に役立っています。
研究の目的
本研究では、さまざまなPETトレーサー(放射性薬剤)を用いて、脳や骨、腫瘍などの代謝や機能の変化を詳細に調べ、より正確な診断法や新しい治療法の開発につなげることを目的としています。
使用する主なPETトレーサー
- [11C]PIB([11C] Pittsburgh Compound B)
アルツハイマー病などに関連するアミロイドβタンパク質の脳内蓄積を可視化するトレーサーです。
認知症の早期診断や発症前段階の研究に用いられています。
- [11C]メチオニン([11C]Methionine)
タンパク質合成に関与するアミノ酸の代謝を反映するトレーサーで、特に脳腫瘍などの悪性度評価や治療効果判定に役立ちます。
- [18F]フッ化ナトリウム([18F]NaF)
骨代謝や骨形成の活性を反映するトレーサーで、骨転移や骨疾患の評価に用いられます。
骨の変化を高感度に捉えることができます。
- [18F]FRP-170([18F]FRP170)
組織の低酸素状態(hypoxia)を検出するトレーサーです。
がん組織や虚血性疾患などにおいて、酸素環境を評価し、治療方針の決定や予後予測に役立ちます。
- [18F]PM-PBB3([18F]PM-PBB3)
タウタンパク質に結合するトレーサーで、アルツハイマー病や前頭側頭型認知症などの神経変性疾患における異常タンパク質の蓄積を可視化します。
脳内でのタウ病理の広がりを直接評価できる、最先端の研究用トレーサーです。
その他の新規または既存のPET薬剤を臨床研究で使用したい場合は、ぜひ当施設までお問い合わせください。
薬の開発に必要な「治験薬GMP対応施設」です。
我々は、アミロイドベータ結合性PET薬剤、腫瘍特異的PET薬剤を活用し、新薬(アルツハイマー病治療薬、抗癌剤)の開発に利用していただきたいと考えています。大分大学医学部附属病院は、病院内に設置された「総合臨床研究センター」を中心として、臨床研究がスムーズに展開できる病院です。